
どうもダルクです
今回はエックス線作業主任者資格取得に向けた、
試験対策を紹介します
クリック応援励みになります↓
なお、今回からnoteの作成も始めました
資格関係の詳しいコンテンツはブログだけではなくnoteでも発信していこうかと思います

作成に手間がかかる具体的な練習問題と解説、
有益なコンテンツは一部有料にしてみようかと思います
御朱印代くらいになればいいかなぁと思います(*’▽’)(笑)
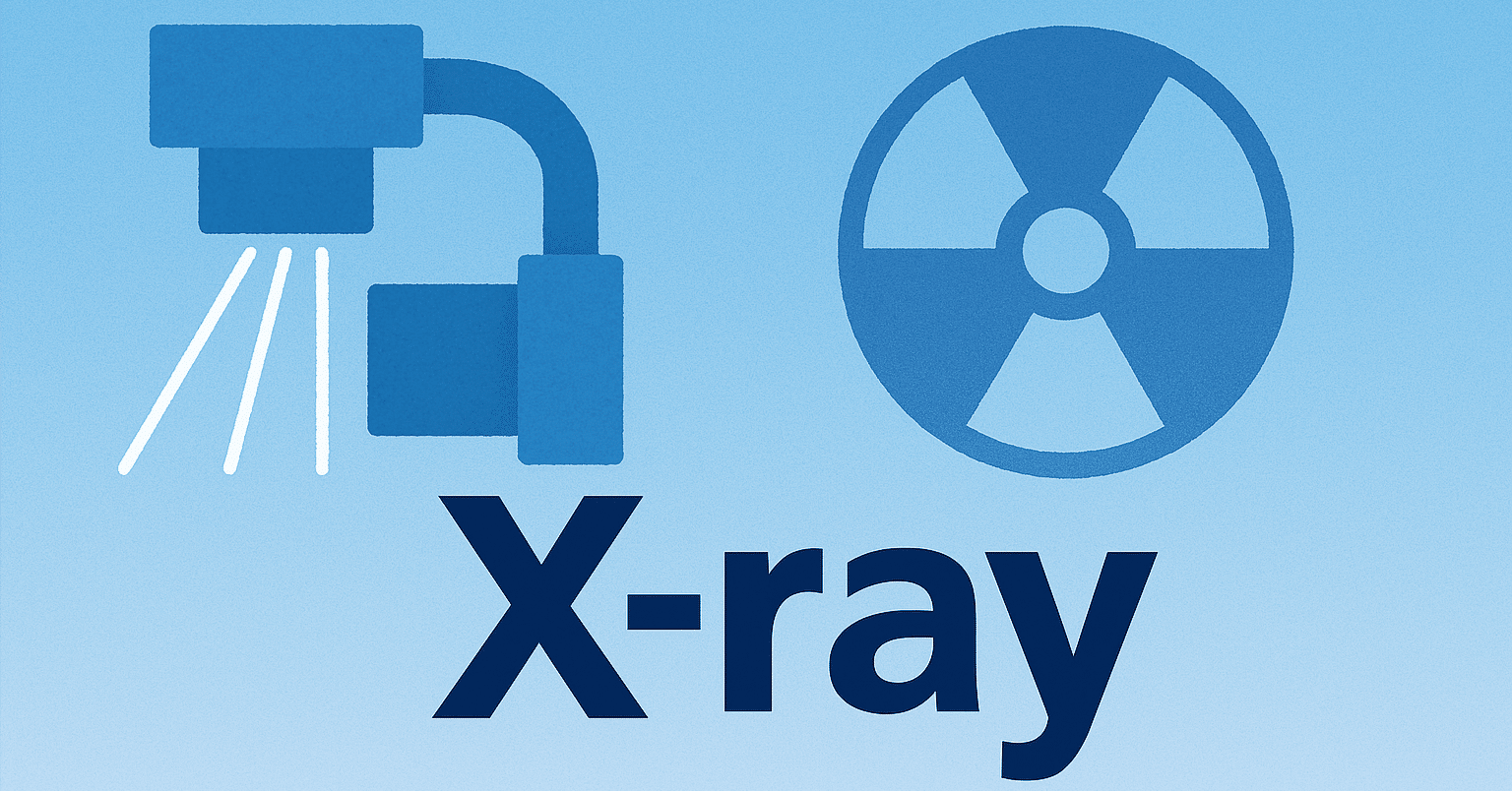
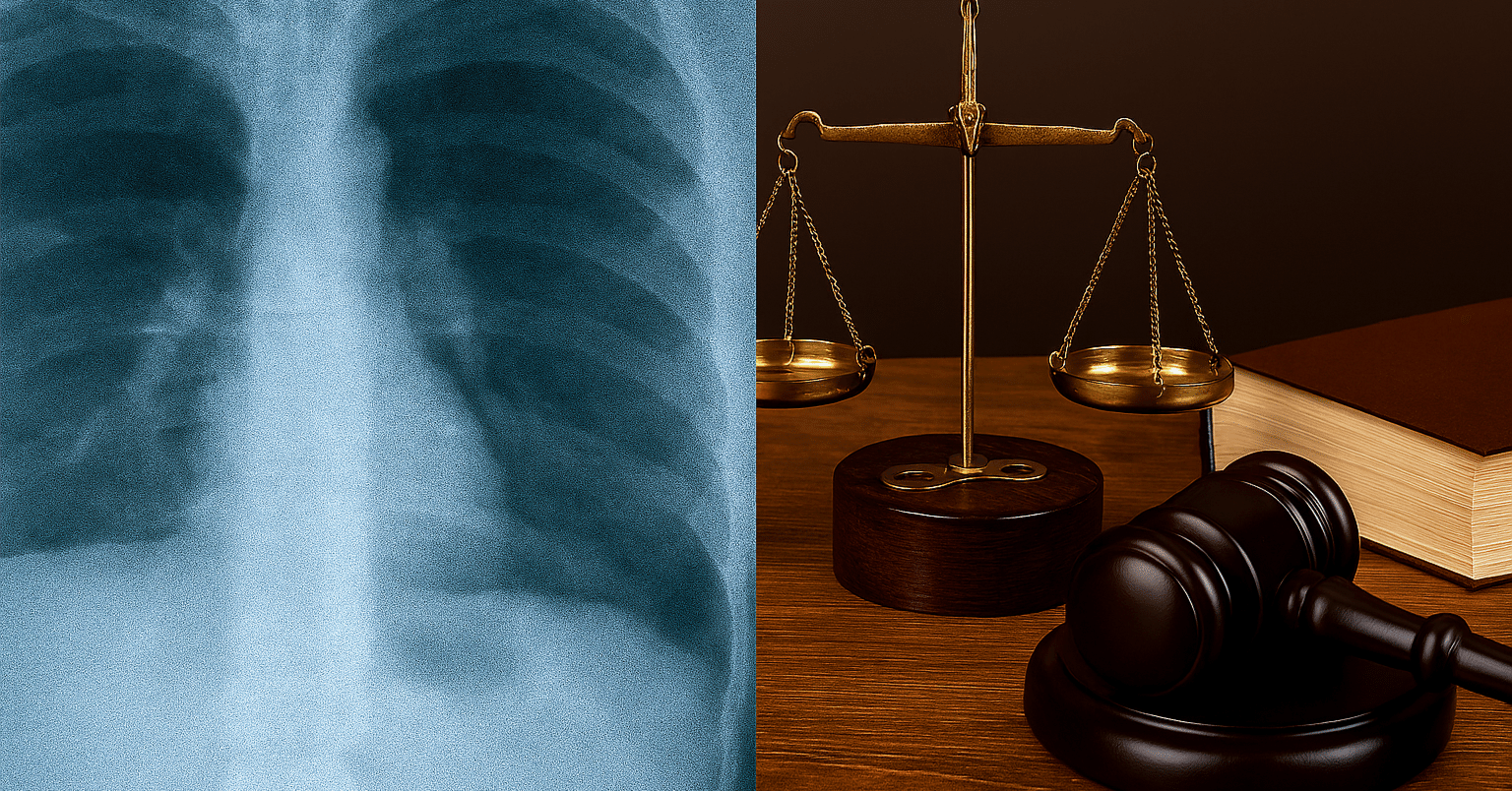
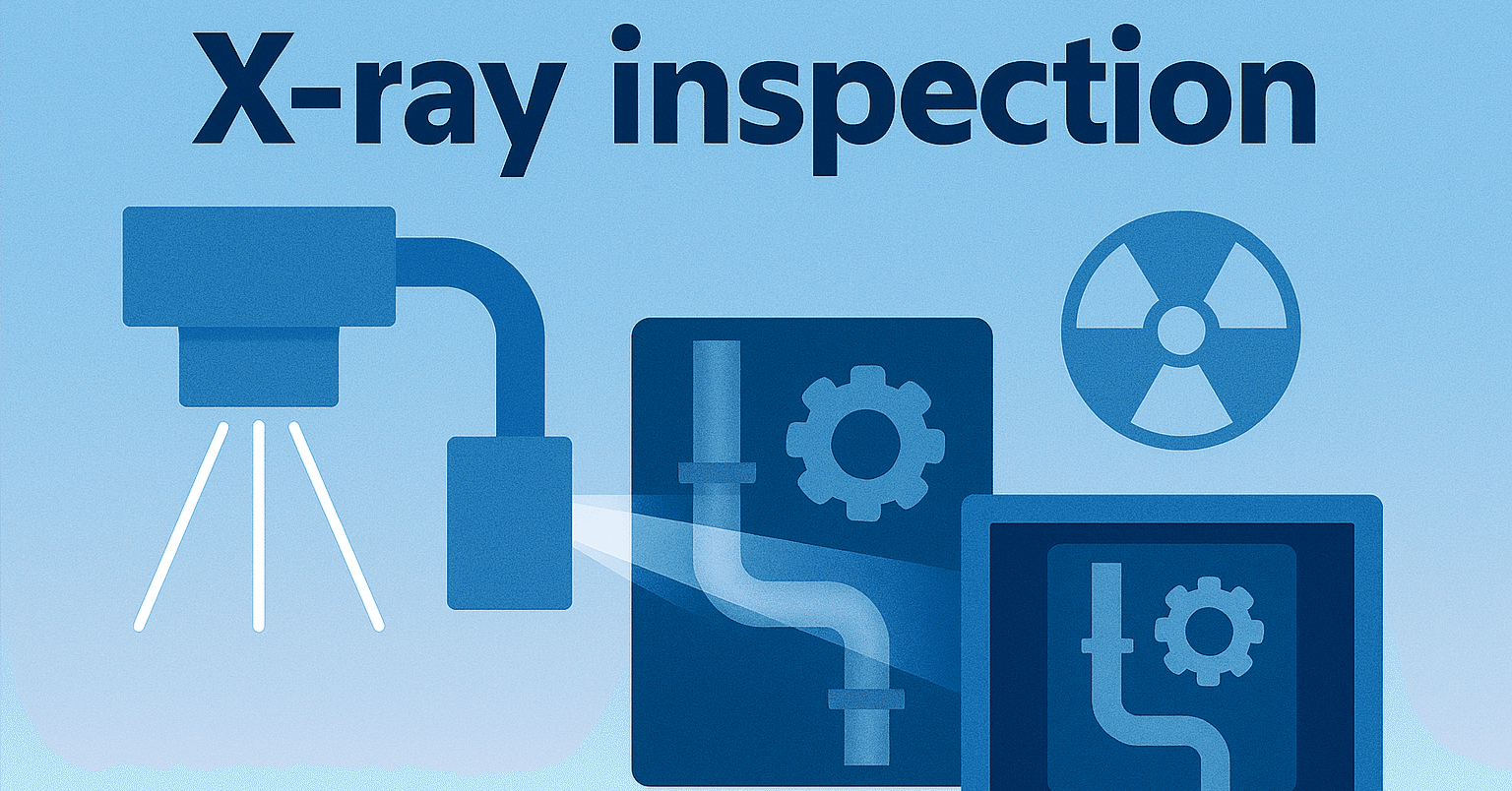
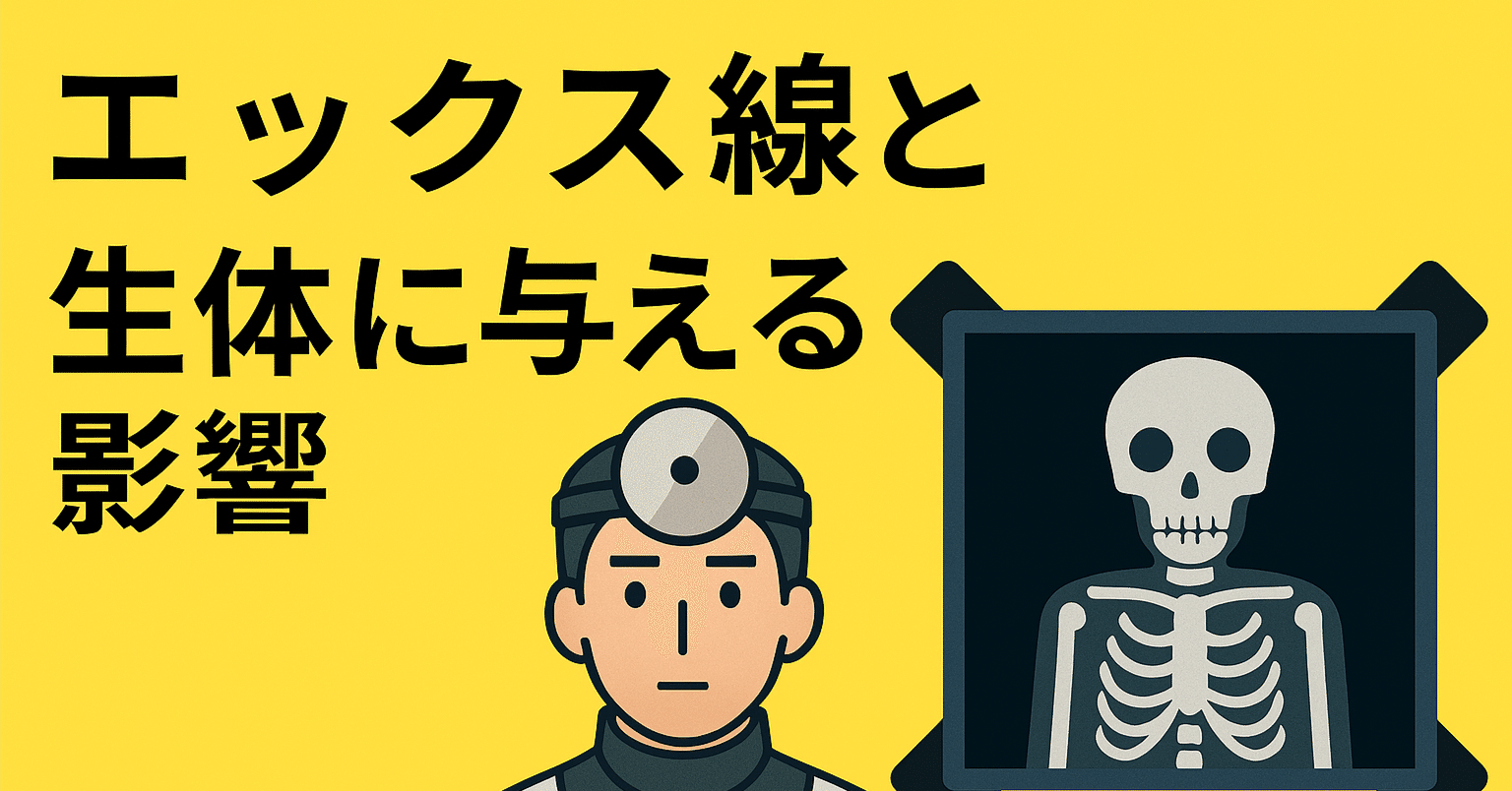
エックス線作業主任者とは
エックス線作業主任者は、公益財団法人安全衛生技術試験協会が発行する労働安全衛生法に基づく国家資格です
詳しい業務内容はコチラ↓
エックス線装置(医療用又は波高値による定格管電圧が1000kV以上の装置を除く。)を用いる作業などを行う場合は、エックス線による障害を防止する直接責任者としてエックス線作業主任者免許を受けた者のうちから、管理区域ごとにエックス線作業主任者を選任することが必要です。
作業主任者は、エックス線による障害の防止の措置の職務に携わります
工業関連の研究機関や製造期間に努める人なら、
組織の指示で取得が求められることがあると思います

私も会社からの要請で受けました(*’▽’)
出題範囲と配点
エックス線作業主任者の出題範囲と出題数、配点の内訳は以下の通りです
| 試験科目 | 出題数 | 配点 |
|---|---|---|
| エックス線の管理に関する知識 | 10 | 30 |
| 関係法令 | 10 | 20 |
| エックス線の測定に関する知識 | 10 | 25 |
| エックス線の生体に与える影響に関する知識 | 10 | 25 |
試験科目ごとの出題数は同じですが配点が微妙に異なり、エックス線の管理に関する知識が一番高配点になっています
エックス線作業主任者の合格基準
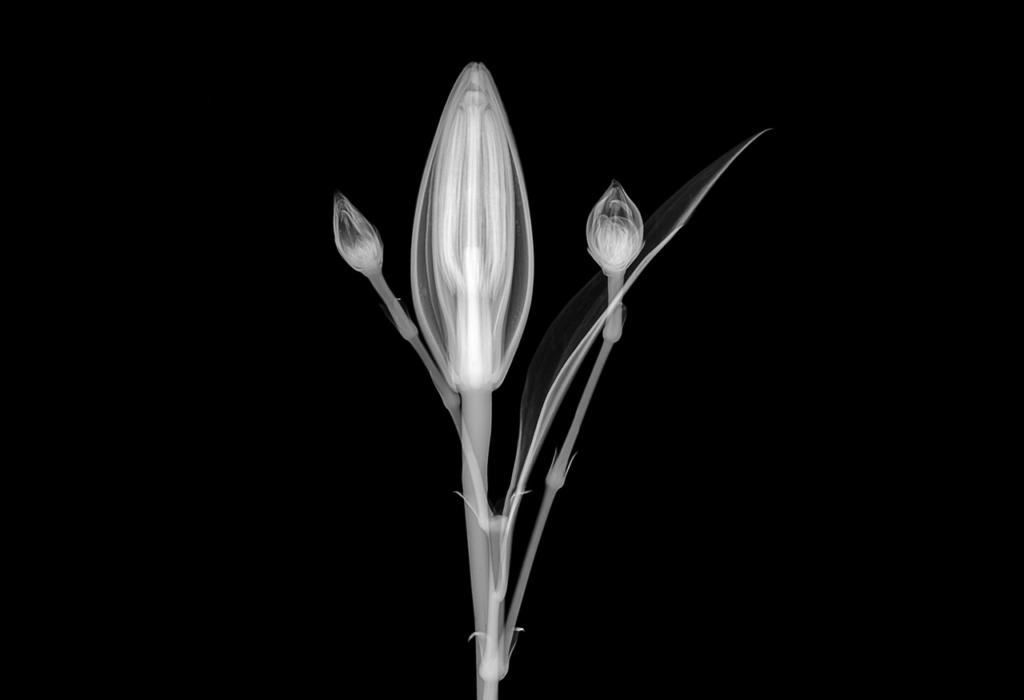
各科目4割以上を得点し、かつ4科目の合計点数が6割以上であること
すなわち、満遍なく点を取る必要があります
出題問題数自体が多くないので、問題の相性によっては事故りやすいです
出題範囲はさほど広くなので、ヤマを張らずに地道に勉強しておきましょう
エックス線作業主任者の難易度と合格率
エックス線作業主任者の合格率は年によって少々のばらつきがありますが、
約45%程度です
一般的な資格の中では決して低い方ではありません
ただし、労働安全衛生関係の免許試験18区分の中では、上から2番目に低い合格率となっており、これまで労働安全衛生関係の資格を取ってきた人にとっては、他よりもはるかに難しいので甘く見ていると普通に落ちます
内容も4つの試験科目ごとにやや難しいポイントがあり、学習にも少々コツがいります

ちょっとだけ物理や統計の問題が出てきます
エックス線作業主任者の試験勉強時間

さて、合格に向けてどのくらいの勉強時間が必要か私見を述べます
まず私の場合は、おそらく50時間ほどかけました
ただ、個人的に合格を目指すだけなら、30時間くらいで十分だったと思います
私の場合は会社から言われて受けたので万が一にも落ちたくなくて、念には念を入れました
ただし必要な勉強時間は個人の能力に寄りますので、あくまでも参考にしてください
エックス線作業主任者 試験対策
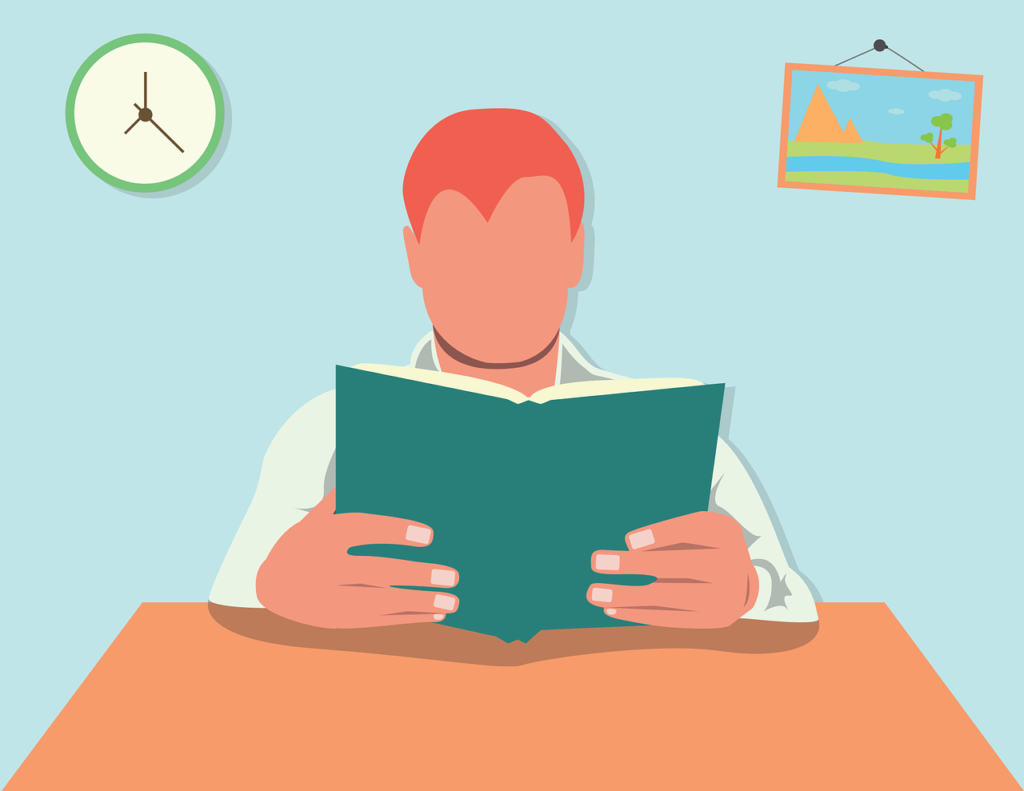
エックス線作業主任者の試験対策について書いていきます
4つの試験科目ごとに抑えるべきポイントを解説していきますが、
まず全体的な留意点を押さえておきます
まず本番の試験問題は全部で10問なのに対して、
試験時間は4時間あります
つまり、時間が足りなくなることはまずありません

私は40分で回答が終わりました(笑)
逆に言うと、時間をかけて考えればわかる問題はあんまりありません
試験前にしっかりとインプットしておかないと、本番でいくら頑張ってもどうにもなりませんのでしっかりと準備しましょう
前述しましたが、4科目の中で1科目でも4割を下回ると不合格なので、
各教科を満遍なく解けるように時間配分しましょう
エックス線作業主任者試験対策①:エックス線の管理に関する知識
まず最初は4科目の中から『エックス線の管理に関する知識』について解説します
4科目の中で唯一30点と他より配点が多いため、合格のためには特に押さえておかなければならない科目といえます
『エックス線の管理に関する知識』と題していますが、
- エックス線とはそもそもなにか
- どのような特徴があってどんな性質があるか
- どんな原理で発生するのか
- どのようなものに活用されているのか
といったエックス線そのものについて、物理的に理解する必要があります
よって物理が苦手な人には難しいかもしれませんが、原理を理解してしまうとあまり暗記しなくて応えられる問題もあります
少なくとも
- エックス線の相互作用
- 制動エックス線と特性エックス線
- 減弱係数と半価層
- ビルドアップ係数
- エックス線利用機器
は特徴を箇条書きにしたり、表にまとめることをお勧めします
例えばエックス線利用機器ではこんな感じ
| 機器 | 利用する原理 |
|---|---|
| 蛍光エックス線分析装置 | 分光 |
| エックス線マイクロアナライザ | 分光 |
| エックス線回折計 | 回折 |
| 応力測定装置 | 回析 |
| ラジオグラフィ | 透過(減弱) |
| 散乱型厚さ計 | 散乱 |
この危機と原理の組み合わせは過去問でも頻繁に問われます
あとこの科目は必ず2問ほど計算問題が出題されます
計算問題はエックス線の減弱に関するものしかありませんし、
出題パターンは3種類くらいしかないので、事前に対策しておけば確実に点を稼ぐことができます
ただし、対策なしだと初見ではかなり難しい(というよりとっかかれない)問題のため、
めちゃくちゃ合否が分かれるポイントだと思います
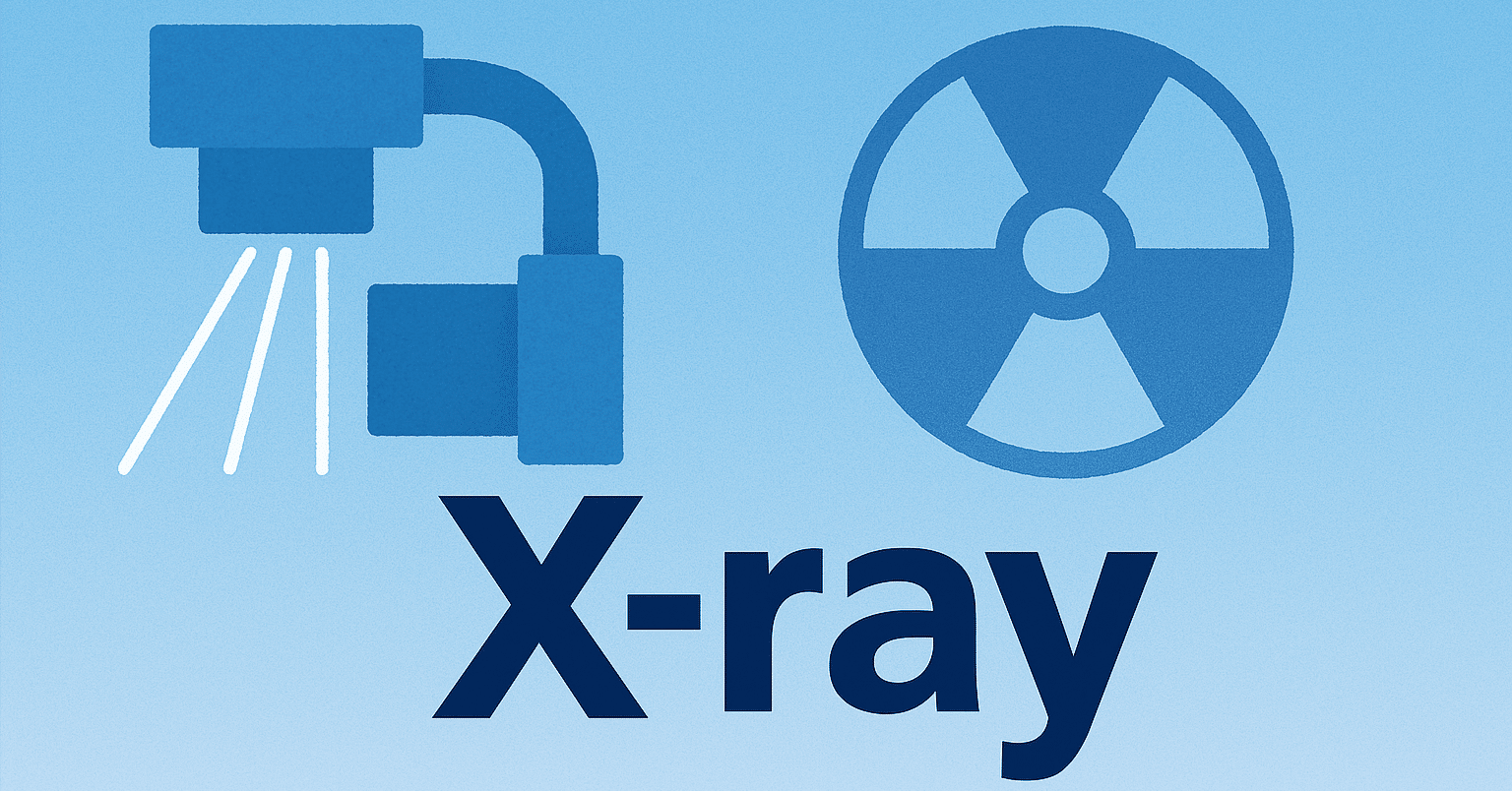
エックス線作業主任者試験対策②:関係法令

関連法令は配点が20点と他の科目より少ないです
個人的に独学で試験に臨む際に、最も学習に時間がかかるのが関連法令です
というのも、法律の条文が詠みにくすぎて全然頭に入ってこないからです

法律の条文ってなんであんなに読みにくいんだ( `ー´)ノ
よって、法令の学習には
- 法令の内容や対象をわかりやすく表にまとめて整理する
- 整理した表をしっかりと記憶する
という二段階で勉強することを強く推奨します
ところがあのまどろっこしい法令の条文をわかりやすく表にまとめるのは、
非常に手間と時間がかかります
そして、表をまとめただけで満足しがちですが、そこからしっかりインプットする作業も必要になります
なので、私は法令の内容を、
- 事業場における安全衛生体制
- 被ばく限度
- エックス縁装置設置場所による安全基準
- 健康診断の対象
- 工業用エックス縁装置の規格
- エックス線作業主任者の職務内容
- 行政へ届け出が必要な事象
などわかりやすくまとめた表を作成しました

表の詳細はnoteのコンテンツで別途公開中です
この表をそのまま覚えれば多くの試験問題に対応可能です
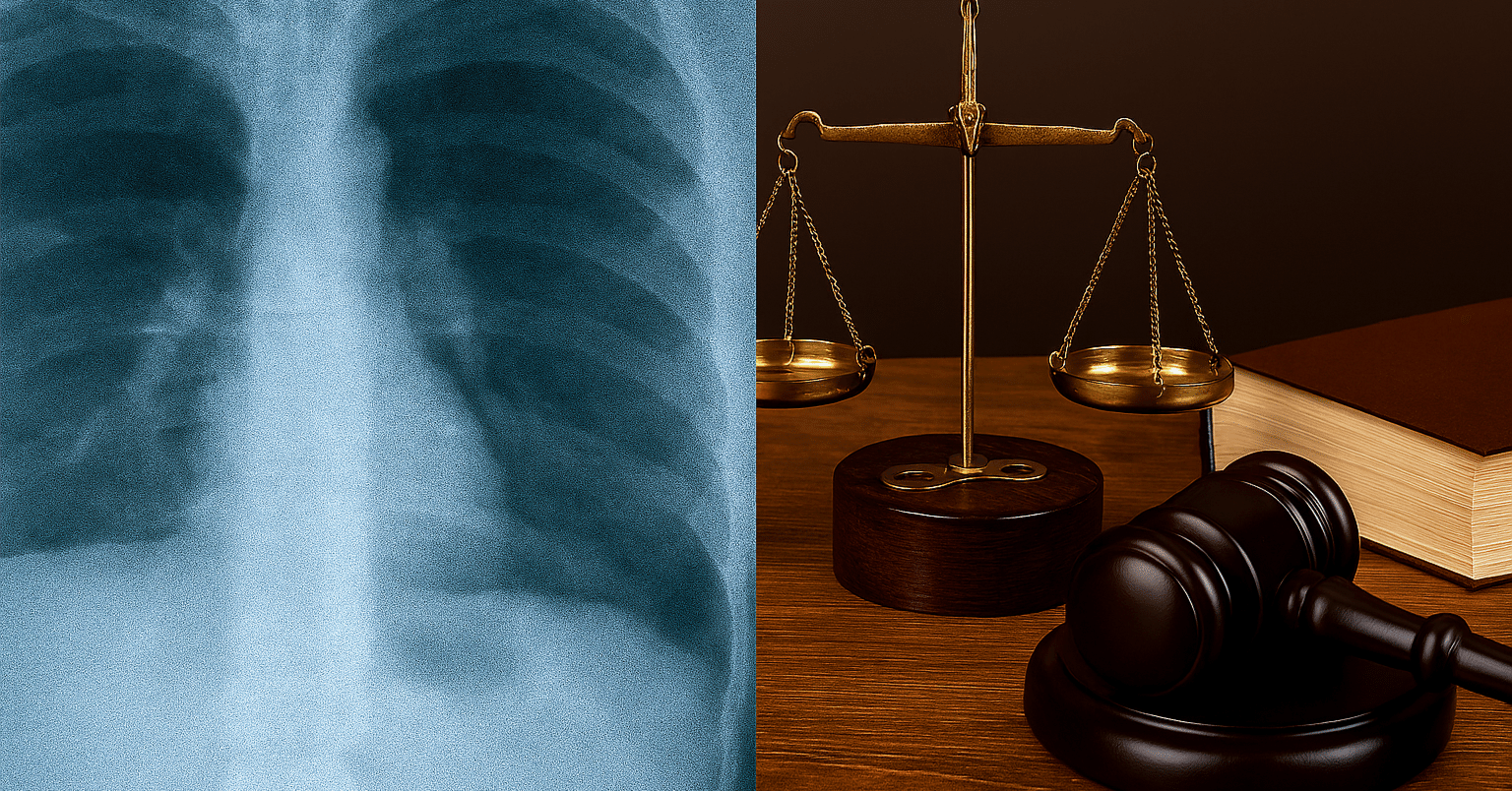
エックス線作業主任者試験対策③:エックス線の測定に関する知識
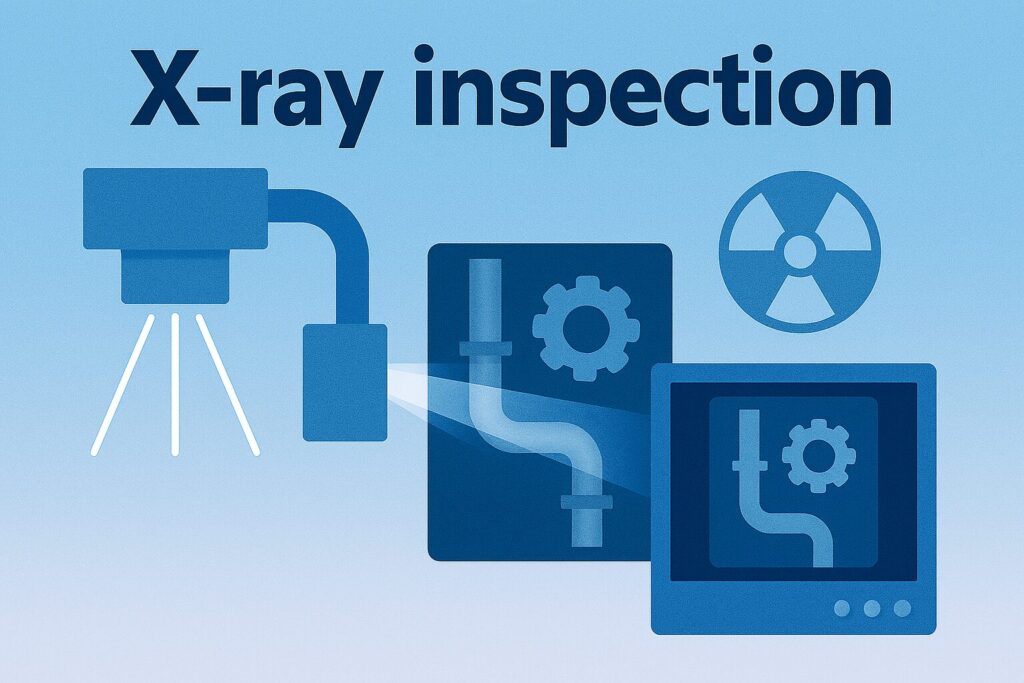
エックス線の測定に関する知識では、多種多様なエックス線の測定器の種類や特徴、測定原理を押さえる必要があります
ところが4科目の中でもっとも理解が難しいのかこの科目です(;・∀・)
というのも、多種多様で複雑なエックス線の測定原理を文字で説明されても、あまりピンと来ないというのが本音です
測定器について理解しないといけないのに、実機を見れないというのも理解が難しい原因の一つであると思います
幸いテストで出題される項目はある程度決まっているので、
各種サーベイメータと個人被ばく線量の特徴を表にまとめることをおススメします
また、
電離箱の1cm線量当量と、GM計数管の真の係数率を求める計算問題も良く出されるので押さえておきたいです
計算自体はめちゃくちゃ簡単なのですが、初見だと全く分からないことが多いと思いますので、
事前に解き方をしっかり理解しておきましょう
例として、標準偏差を求める問題が出ます
放射線測定器で計数測定したとき、
計数値をN、それに要した時間をt、計数率をnとすると、
計数値の標準偏差は
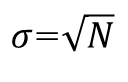
計数率の標準偏差は
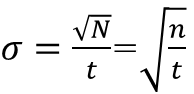
となります
覚えていれば簡単です
なお、過去問の中には計数率の相対偏差を聞いてくることがあります
かなりいやらしいひっかけなんで注意が必要です
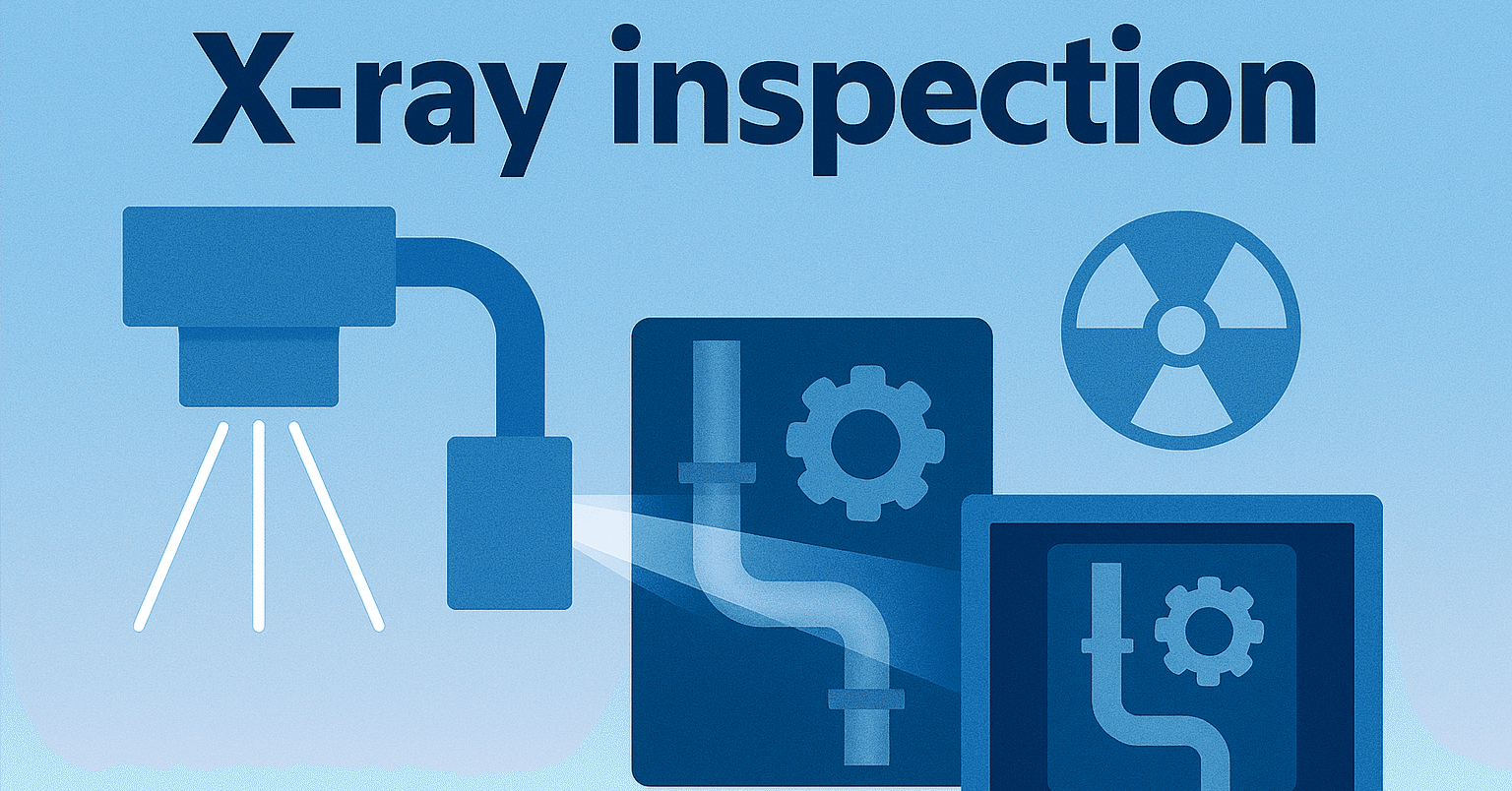
エックス線作業主任者試験対策④:エックス線の生体に与える影響に関する知識
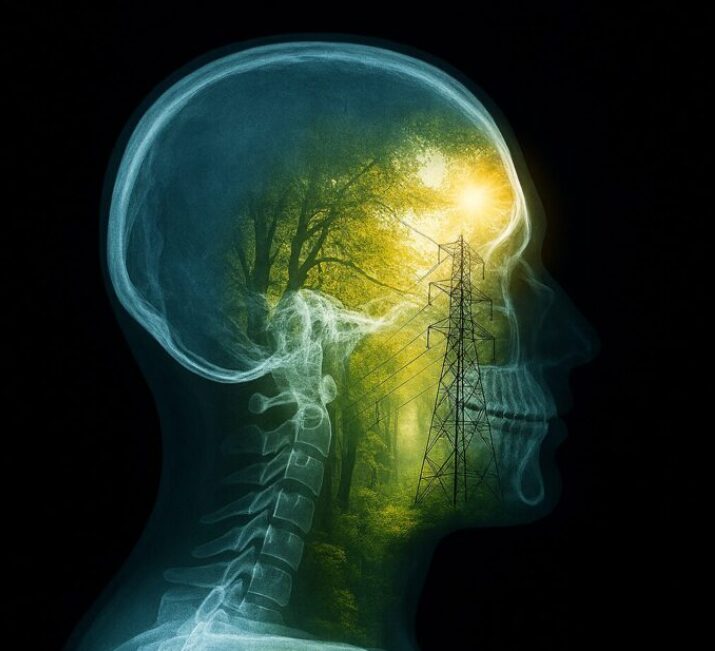
最後はエックス線の生体に与える影響に関する知識についてです
これに関しては概ね試験で出題される問題が大きく変わらないので、
過去問を中心に知識を整理していけば大丈夫です
計算問題も出ません
ただ、覚えることは少なくないのでコツコツ学習していきましょう
エックス線の生体に与える影響に関する知識については明確に出題傾向が偏っているので、
以下を中心に知識を整理すると効率がいいと思います
- 放射線感受性の比較
- 直接作用と間接作用の比較
- 確定的影響と確率的影響の比較
- LET
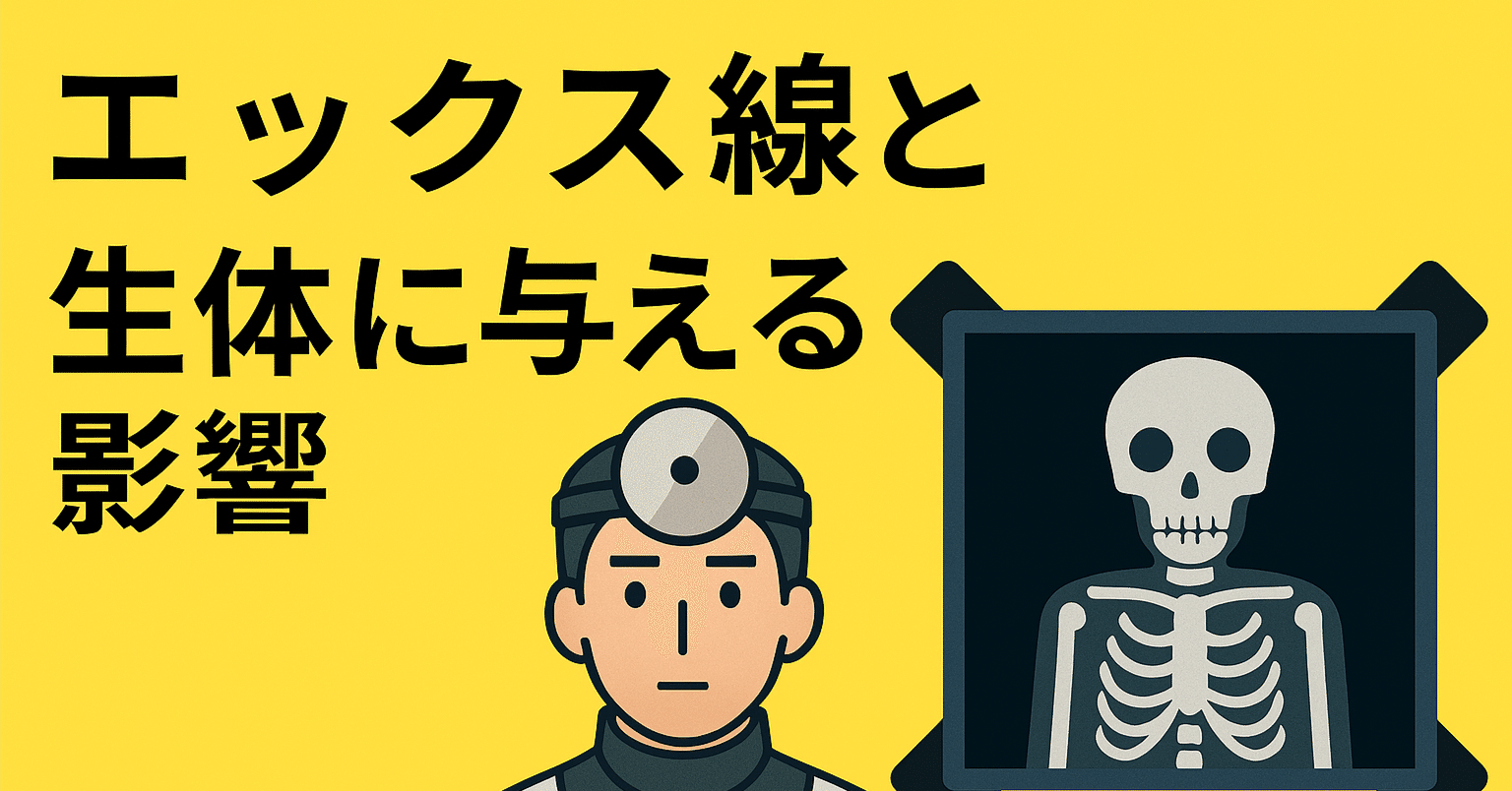
おわりに
ここではあくまでエックス線作業主任者試験に合格するための勉強方法と学習を進めるコツ、
必要な学習時間などを中心に紹介しました
具体的な練習問題とその解説、計算問題の解放、暗記と整理に有効な表については、
今後当ブログの別記事やnoteの方で拡充していこうと思います
では、健闘を祈ります

BlogMapの登録してくれると嬉しいです
記事が増えます(/・ω・)/

クリック応援励みになります↓
人気ブログランキング
postprimeはコチラ↓

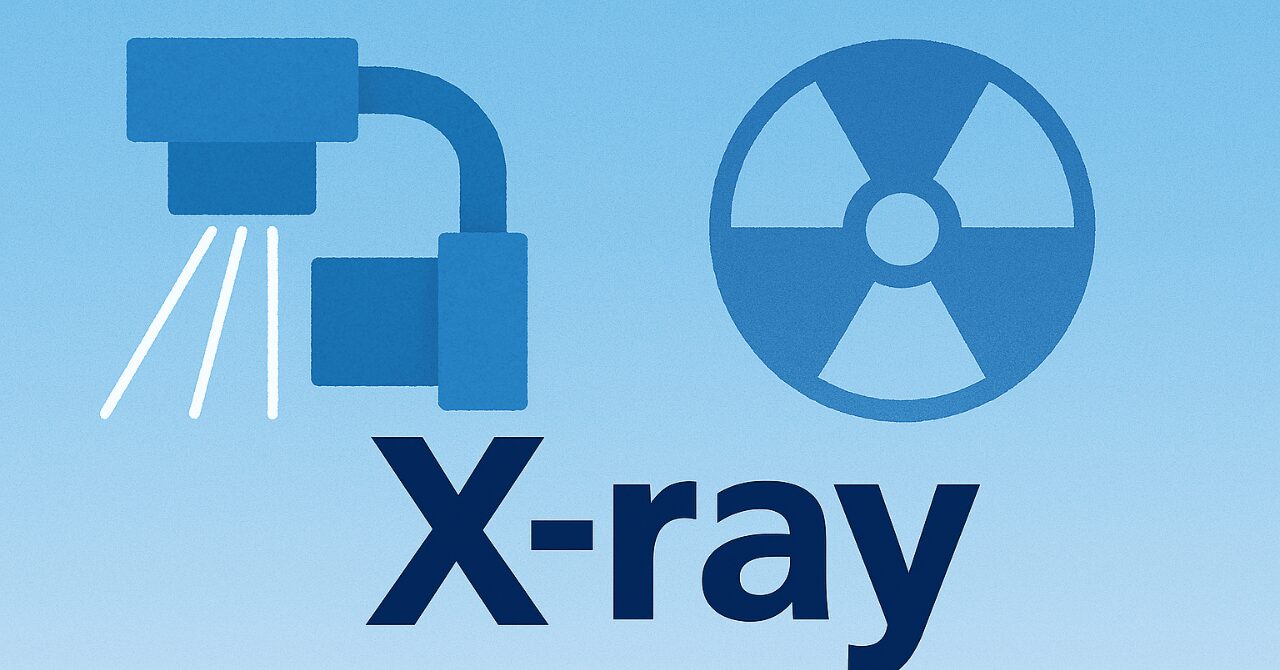


コメント